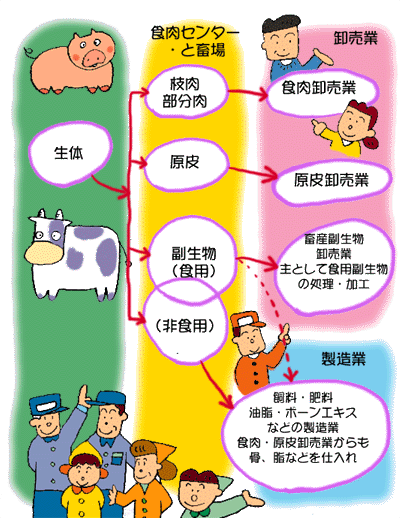| |
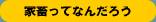
●お肉になる牛の品種いろいろ
●お肉になる豚の品種いろいろ
●お肉になる鶏の品種いろいろ
●珍しい?おなじみ?特用家畜の肉
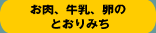
●お肉がお店に並ぶまで
●副生物がお店に並ぶまで
●卵がお店に並ぶまで
●牛乳がお店に並ぶまで
●輸入食肉がお店に並ぶまで

●食物の安全性を高めるHACCP
●国産肉も輸入肉も厳しく検査!
●化学物質の残留も厳しくチェック
●格付けが影響する食肉の価格
●分かりやすい表示で、お買い物も簡単に
●上手にお買いもの、良い店と肉の選び方
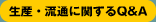
●Q&A
|
|
| 副生物がお店に並ぶまで |
| |
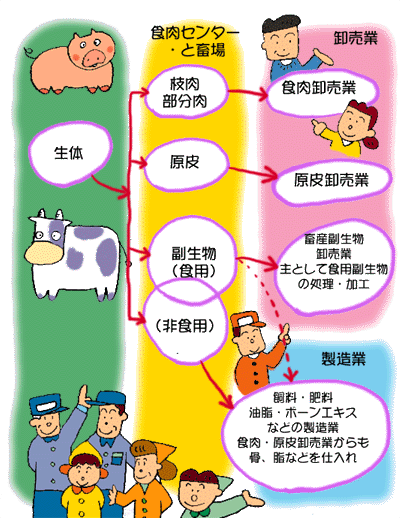 |
副生物ってなんだろう |
生体から枝肉を生産した後に残る副産物から、原皮を除いた内臓類が副生物です。バラエティミートと呼ばれることもあります。
日本では一般的にホルモン、モツなどと呼ばれ、主に焼き鳥屋で消費されていますが、家庭ではあまり食べられていません。日本以外、例えばアメリカやオーストラリアでは、ファンシーミートなどとも呼ばれ、安くて経済的、栄養成分が豊か、変化に富んだ味わいなどの理由から食肉同様親しまれています。アジアでは、肝臓、腎臓、心臓、尾などが食肉より貴重なものとして消費されるところもあります。
牛の副生物には、ハツ(心臓)、レバー(肝臓)、マメ(腎臓)、ミノ(第一胃)、センマイ(第三胃)、ハラミ(横隔膜)、サガリ(横隔膜)、ヒモ(小腸)、シマチョウ(大腸)、タン(舌)、カシラニク(頭肉)、テール(尾)などがあります。これらの多くは焼肉の食材に使われ、大腸、小腸類はモツ煮込みなどに使われています。
豚の副生物は、関東方面では串焼きの食材にされ、大腸、小腸類は、牛同様モツ煮込みになります。レバーは、牛、豚ともにペースト状にしたり、ムース状にしたり、離乳食に加工されたりして幅広く利用されています。
一般的に、内臓の消費は肉と同様、西では牛、東では豚が多く、冬場は白物(腸や胃などの消化器系統)がモツ煮やホルモン焼きに、夏場は赤物(レバー、ハツ、サガリ)が焼肉などの材料になるなど、季節性が反映される傾向にあります。 |
地域流通が行われる副生物 |
副生物の流通は、保存性が低いことから、地域流通が主体です。牛、豚の副生物のうち、食用のものは、畜産副生物卸売業で取り引きされます。副生物は、と畜解体の段階で副次的に産出されるので、出荷をコントロールできません。
また保存性が低く、腐敗が急速に進み、検査による廃棄率が高いことから、歩留まり率も低くなっている、流通が難しい食品です。
鶏の副生物については例外で、インテグレーターが一括して鶏肉と副生物の流通を行ないます。
|
●関連情報(冊子)
|
|